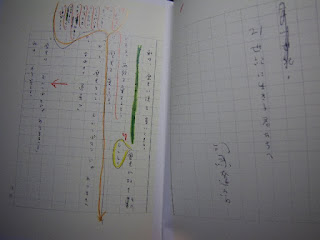(司馬遼太郎記念館 発行)より引用。
私は歴史小説を書いてきた。
もともと歴史が好きなのである。両親を愛するようにして、
歴史を愛している。
歴史とはなんでしょう、と聞かれる時、
「それは、大きな世界です。かって存在した何億という人生が
そこにつめこまれている世界なのです」と、答えることにしている。
私には、幸い、この世にすばらしい友人がいる。
歴史の中にもいる。そこには、この世で求めがたいほどに
すばらしい人たちがいて、私の日常を、はげましたり、
なぐさめたりしてくれているのである。
だから、私は少なくとも二千年以上の時間の中を、
生きているようなものだと思っている。この楽しさは
--もし君たちさえそう望むなら--おすそ分けして
あげたいほどである。
ただ、さびしく思うことがある。
私が持っていなくて、君たちだけが持っている大きなものがある。
未来というものである。
私の人生は、すでに持ち時間が少ない。例えば、二十一世紀という
ものを見ることができないにちがいない。
君たちは、ちがう。
二十一世紀をたっぷり見ることができるばかりか、
そのかがやかしいにない手でもある。
もし「未来」という町角で、私が君たちを呼びとめることが
できたら、どんなにいいだろう。
「田中君、ちょっとうかがいますが、あなたが今歩いている
二十一世紀とは、どんな世の中でしょう。」
そのように質問して、君たちに教えてもらいたいのだが、
ただ、残念にも、その「未来」という町角には、
私はもういない。
だから、君たちと話ができるのは、今のうちだという
ことである。
もっとも、私には二十一世紀のことなど、
とても予測できない。
ただ、私に言えることがある。それは、歴史から
学んだ人間の生き方の基本的なことどもである。
昔も今も、また未来においても変わらないことがある。
そこに空気と水、それに土などという自然があって、
人間や他の動植物、さらには微生物にいたるまでが、
それに依存しつつ生きているということである。
自然こそ不変の価値なのである。なぜならば、
人間は空気を吸うことなく生きることができないし、
水分をとることがなければ、かわいて死んでしまう。
さて、自然という「不変のもの」を基準に置いて、
人間のことを考えてみたい。
人間は--くり返すようだが--自然によって
生かされてきた。
古代でも中世でも自然こそ神々であるとした。
このことは、少しも誤っていないのである。
歴史の中の人々は、自然をおそれ、
その力をあがめ、自分たちの上にあるものとして
身をつつしんできた。
この態度は、近代や現代に入って少しゆらいだ。
--人間こそ、いちばんえらい存在だ。
という、思いあがった考えが頭をもたげた。
二十世紀という現代は、ある意味では、自然への
おそれがうすくなった時代といっていい。
同時に、人間は決しておろかではない。
思いあがるということとはおよそ逆のことも、
あわせ考えた。つまり、私ども人間とは自然の
一部にすぎない、というすなおな考えである。
このことは、古代の賢者も考えたし、また十九世紀の
医学もそのように考えた。ある意味では平凡な事実に
すぎないこのことを、二十世紀の科学は、
科学の事実として、人々の前にくりひろげてみせた。
二十世紀末の人間たちは、このことを知ることによって、
古代や中世に神をおそれたように、再び自然を
おそれるようになった。
おそらく、自然に対しいばりかえっていた時代は、
二十一世紀に近づくにつれて、終わっていくにちがいない。
「人間は、自分で生きているのではなく、大きな存在に
よって生かされている」
と、中世の人々は、ヨーロッパにおいても東洋においても、
そのようにへりくだって考えていた。
この考えは、近代に入ってゆらいだとはいえ、近ごろ再び、
人間たちはこのよき思想を取りもどしつつあるように思われる。
この自然へのすなおな態度こそ、二十一世紀への希望であり、
君たちへの期待でもある。そういうすなおさを君たちが持ち、
その気分をひろめてほしいのである。
さて、君たち自身のことである。
君たちは、いつの時代でもそうであったように、
自己を確立せねばならない。
--自分にきびしく、相手にはやさしく。
という自己を。
そして、すなおでかしこい自己を。
二十一世紀においては、特にそのことが重要である。
二十一世紀にあっては、科学と技術がもっと発達するだろう。
科学・技術が、こう水のように人間をのみこんでしまってはならない。
川の水を正しく流すように、君たちのしっかりした自己が、
科学と技術を支配し、よい方向に持っていってほしいのである。
右において、私は「自己」ということをしきりに言った。
自己といっても、自己中心におちいってはならない。
人間は助け合って生きているのである。
私は、人という文字を見るとき、しばしば感動する。
ななめの画がたがいに支え合って、構成されているのである。
そのことでも分かるように、人間は、社会をつくって生きている。
社会とは、支え合う仕組みということである。
原始時代の社会は小さかった。家族を中心とした社会だった。
それがしだいに大きな社会になり、今は、国家と世界という
社会をつくり、たがいが助け合いながら生きているのである。
自然物としての人間は、決して孤立して生きられるようには
つくられていない。
このため、助け合う、ということが、人間にとって、
大きな道徳になっている。
助け合うという気持ちや行動のもとのもとは、
いたわりという感情である。
他人の痛みを感じることと言ってもいい。
やさしさと言いかえてもいい。
「いたわり」
「他人の痛みを感じること」
「やさしさ」
みな似たような言葉である。
この三つの言葉は、もともと一つの根から出ているのである。
根といっても、本能ではない。だから、私たちは訓練を
してそれを身につけねばならないのである。
その訓練とは、簡単なことである。例えば、友達がころぶ。
ああ痛かったろうな、と感じる気持ちを、そのつど自分の中で
つくりあげていきさえすればよい。
この根っこの感情が、自分の中でしっかり根づいていけば、
他民族へのいたわりという気持ちもわき出てくる。
君たちさえ、そういう自己をつくっていけば、二十一世紀は
人類が仲よしで暮らせる時代になるにちがいない。
鎌倉時代の武士たちは、
「たのもしさ」
ということを、たいせつにしてきた。人間は、いつの時代でも
たのもしい人格を持たねばならない。人間というのは、
男女とも、たのもしくない人格に魅力を感じないのである。
もう一度くり返そう。さきに私は自己を確立せよ、と言った。
自分にきびしく、相手にはやさしく、とも言った。いたわり
という言葉も使った。それらを訓練せよ、とも言った。
それらを訓練することで、自己が確立されていくのである。
そして、”たのもしい君たち”になっていくのである。
以上のことは、いつの時代になっても、人間が生きていく上で、
欠かすことができない心がまえというものである。
君たち。君たちはつねに晴れあがった空のように、たかだかと
した心を持たねばならない。
同時に、ずっしりとたくましい足どりで、大地をふみしめつつ
歩かねばならない。
私は、君たちの心の中の最も美しいものを見つづけながら、
以上のことを書いた。
書き終わって、君たちの未来が、真夏の太陽のように
かがやいているように感じた。